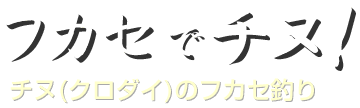 大阪湾・南港/堺/浜寺運河/泉大津/岸和田/貝塚/泉佐野の波止からフカセ釣りや紀州釣りでチヌ(クロダイ)・グレ(メジナ)を狙っています。
大阪湾・南港/堺/浜寺運河/泉大津/岸和田/貝塚/泉佐野の波止からフカセ釣りや紀州釣りでチヌ(クロダイ)・グレ(メジナ)を狙っています。
「5号の道糸に最新のウキ、1.5号の道糸にスーパーボールだとどちらが良く釣れるでしょう?」
 釣りを始めたばかりの人は、道糸のことについてほとんど考えないと思います。リールについている糸、ハリスとは違う種類で、ハリスより太いもの・・・ぐらいしか考えていないような感じです。事実、私もそうでしたし、あまり釣りをしない人も道糸には無頓着であることが多いように見受けられます。
釣りを始めたばかりの人は、道糸のことについてほとんど考えないと思います。リールについている糸、ハリスとは違う種類で、ハリスより太いもの・・・ぐらいしか考えていないような感じです。事実、私もそうでしたし、あまり釣りをしない人も道糸には無頓着であることが多いように見受けられます。
買ったときにおまけでついている糸が、スプールの底にちょっとだけ残っている状態でも釣りは出来ますが・・・
ところが、だんだん釣りになれてくると道糸が思い通りにさばけない事が苦痛となってきます。たとえばあそこまで飛ばしたいけど飛ばない、風が強くて道糸にウキが引っ張られる、仕掛けが馴染まない、巻きグセがひどくて、いつの間にか仕掛けが絡んで大お祭り大会・・・などど道糸がしっかりしていれば起き得ないようなことが頻発します。また、強度の落ちた道糸だと、アワセ切れや、ひどいときには合わせる前に結合部から切れてしまったこともあります。
おろしたての道糸は快適に使えますが、2時間もすればガイドにこすれる音がザラザラとしてくるようになります。また、ちょっとしたもつれなどで道糸に癖が付いてしまうと最近の軽い仕掛けだと馴染まなくなったりします。こういうときは、10mほど道糸を切り落とすと気分もさっぱりして釣りに集中できます。
ナイロン道糸にはそれぞれ特性があります。大きく分けると、サスペンドとフロートの2種類になります。
の2種類になります。また、この中間の特性を持つセミフロートもあります。
基本的にはサスペンドタイプが有利なシチュエーションが多いと感じます。沈め探りや全層ならばサスペンドかセミフロートを使います。
タイプそれぞれの特性を理解し、サスペンドとフロートの2種類を釣り場に持ち込めば強風以外なら何とか釣りになると思います。
道糸にはそのほかPEライン、フロロカーボン道糸があります。それぞれうまく使えばいろいろな状況に対応しやすいと考えますが、まずはナイロンラインから始めることがいいと思います。
などの問題が出ますので、ナイロン道糸がベースで、PEにナイロンリーダーかフロロカーボンリーダーをセットするパターンがチヌ釣りには向いていると思います。PE直結は、私の場合重く大きな棒ウキである遠矢ウキを使うことを前提として仕掛けを組むのでちょっと考えづらいところですし、PEはサルカンとの結束強度がきわめて弱いのでラインシステムを組むやり方が強度が安定すると考えています。
ナイロンはもちろん、PEもフロロカーボンも使いましたけども、ナイロンで釣れる条件ならナイロン使うことで素直な釣りができると感じています。
フカセ釣りで使う道糸にはナイロン以外にはPEとフロロカーボンがあります。ウキフカセ釣り以外ではPEもしくはフロロカーボンが当たり前になっていますが、初期の製品はどちらもウキフカセ釣りに向いていませんでした。
現在市販されている磯釣り用PEは、PEなのに比重とコシがあり、その細さによる遠投性、風の影響の少なさなど十分にメリットを享受できる様になっています。細いのに絡まない、不思議な糸ですよ。
フロロカーボンもスプールへの馴染みが良くなり、ちょっと固めの道糸という感触で使えるようになっています。
PEは道糸の細さが決め手となるとき、フロロカーボンは比重が決め手となるときに用いると、釣り方の幅がぐっと広がります。
まずはPEのメリットとして、ナイロンに比べて引張強度が強いため糸を細くすることができます。すると風や潮の影響を受けにくく、遠投しやすくなります。つまり、ナイロンでは流しづらい条件や、届かないポイントでもPEならば釣りになるということです。また、伸びも無いので、小さなアタリもダイレクトに伝わります。
では、なぜ今までPEがメジャーにならなかったかというと、 今までのPEは、テンションを掛けっぱなしの釣り、ルアー釣り、船釣り、投げ釣りなど、糸がたるむ時間が殆ど無い釣り用に開発されていたので、糸のコシがなく、フカセ釣りのように張らず緩めずの釣り方だと穂先などに絡んでしまうものでした。また、比重も海水に浮いてしまうものばかりだったので、特定の条件下以外ではPEは使われることはありませんでした。
ところが、昨今の技術革新により、PEなのに海水に沈み、かつナイロンより細いのに腰のある糸が開発され、このおかげで、PEをウキフカセ釣りに使えるようになりました。
PEはナイロンより高価のように思われるでしょう。実際、釣具店ではナイロンの2倍~3倍で販売されていることが多いですね。ですけど、PEは吸水劣化もなく、釣行回数が多い人でも1年に1度巻きかえるか、切り落として残りが少ないから巻きかえるぐらいで十分強度が維持できる物となっていますので、ランニングコストは下手しなくともPEのほうが安くなります。
メリットばかりのPEのように見えますが、欠点もあります。
PEの最大の欠点は、ナイロンやフロロカーボンに比べると結び目の強度が極端に落ちることですね。ナイロンの結びで結束した場合、直線強度の6割程度しか出ません。なので、PEの使いこなしは結びのマスターにかかっていると言っても良いでしょう。
私は大知昭さんのように直接PEにウキを通し、サルカンに結ぶことはしていませんので、PEにリーダー4~5ヒロをとって仕掛けを作っています。PEとリーダーの結合にはFGノットやノーネームノットなど強い結束方法はたくさんありますが、磯釣り・波止釣りではその他にも結束部分がたくさんあるので、結びにかける時間と強度のバランスは各自、いろいろ試してみてください。
ちなみに私はトリプルエイトノット(チチワ結びで3回ねじる)でハーフヒッチ(昔で言うクッション結び)を6~10回にしています。強度に関する自信はまだありませんけど、これで思った通りの強度バランスは出ているし、特殊な結び方をマスターする必要もなく、現地で結んでもさほど時間がかからないので今のところはこれでよいと感じています。
フロロカーボン自体は新しい糸でもないのですが、あの硬さが仇となってスピニングリールのスプールに馴染まず、使いづらいものでしたが、こちらもPE同様、道糸として普通に使われるようになったため、スピニングにも馴染みやすいものになりました。
フロロの使い所としては、サスペンドでも風に流されてしまうときや、流れが速いときの沈め探りに用います。こちらも、ナイロンに比べて伸びないので、アタリがダイレクトに伝わります。ただし、うまく道糸を張らないと手前から沈みすぎて根に掛かる恐れがあります。
PEとは違い、結び方などに違いがあるわけでもないので、チャレンジするには簡単かと思います。
強度や比重の点から、PEとフロロさえあれば全て対応できそうですが、ナイロン道糸はPEにもフロロにもない特性があります。
それは、ナイロンは自らが伸び、クッションの役目を果たすことです。
PEやフロロカーボンを道糸に使うと、その伸びの無さはアタリのダイレクト感に繋がります。しかしながら必要以上に硬いタックルだと、魚は逃れようと必死に抵抗します。
最近の竿はぐっと胴に入って「いなす」ようになっています。気づいたら空気を吸っていた、というところでしょうか?磯や波止の根回りに住むチヌやグレでは、強引なやり取りがバラしにつながることはよくあります。
ところが、ナイロン道糸をベースに調子を決定した竿でPEやフロロカーボン道糸を使うと、魚が暴れやすいと感じますし、いつもよりハリスの号数が1ランク下がった程度の負荷で飛んでしまいます。
なので、ナイロン道糸で釣りができる状況であれば、ナイロンを選択するほうが現段階では賢明なのではないかと感じていますので、これ以下の項目ではナイロン道糸を用いることを前提とします。
当たり前ですけど、道糸は
わけですから、やたら細くても太くても駄目です。必要な強度+若干の余裕をもって号数選定する必要があります。必要な強度は、そのほかの釣具・タックルとのバランスを考えながら選定します。
道糸とハリスのバランスですが、まず大前提として以下のことを覚えてください。
以上のことを鑑みて、ナイロン道糸とフロロカーボンハリスのバランスで良いと思われる組み合わせは、
だと私は考えます。根掛り多発地帯で竿を出すときや、 ナイロンハリスを使うのであれば、道糸をさらに1ランク上げてやっても良いかもしれません。強風下でどうしても釣りをしなければならないときは、ウキをロストするのを覚悟の上、ハリスと同じか、1ランク細い道糸を使うことにより釣れる確率がアップするのは言うまでもありません。
 ナイロン、フロロは一回釣りに行くたびに最低限10m、長いときで竿3本(15m・・・タナを5ヒロとか6ヒロで釣ったとき)ほど捨てます。これを忘れないためには、納竿時に竿を伸ばしたままウキを手に取り、そしてその状態のままスプールの爪にラインを固定してその先を切り取ることを習慣付けておけば切り損ねることはありません。細い道糸を使う機会が増えたので、きちっと傷や巻きグセをチェックしておかないとトラブルの元になります。
ナイロン、フロロは一回釣りに行くたびに最低限10m、長いときで竿3本(15m・・・タナを5ヒロとか6ヒロで釣ったとき)ほど捨てます。これを忘れないためには、納竿時に竿を伸ばしたままウキを手に取り、そしてその状態のままスプールの爪にラインを固定してその先を切り取ることを習慣付けておけば切り損ねることはありません。細い道糸を使う機会が増えたので、きちっと傷や巻きグセをチェックしておかないとトラブルの元になります。
PEはそのまま持って帰って、メンテナンス後にリーダーを組みなおします。
そして帰宅後に塩抜きをするのですが、以前はスプールごと水に3分ぐらい漬けて塩抜きをしていましたが、このやり方だと、ナイロンの強度低下が著しく出るように思えます。何年かずっと漬けてやっていたのですが、近頃は漬けることはせず、さっとシャワーで流すだけにしたところ、強度低下はあまり感じられなくなりました。なので、厳密にいえば漬けずに一度引き出して濡れタオルでふき取るぐらいがベストな方法かと思います。
PEは吸水しないのでどんどん漬けて、2~3回に一度はPEメンテナンススプレーを吹付しておきましょう。このスプレーをするとしないでは糸の出方が全然違います。 そして、リーダーを組みなおします。
ナイロン、フロロ道糸の交換頻度についてですが、毎回巻き替える人もいます。が、通常マメな人で、2~3回ぐらいで巻き変えているようです。ここでちょっと考えてみてください。使ってもいない、ただ巻き癖だけが付いた糸が無駄だと感じませんか?昔は巻き変えて反対から使っていたのですけど、この方法だとつぶれ、ヨレがどうしても気になります。
釣り業界の豆知識ですが、メーカーテスターとはいえすべての釣具を無償で提供されているわけではないようで、消耗品は自前の方が多いようです。その人たちもやっていることは、1巻き150mで売られている道糸を半分ずつ使うことです。大知昭黒鯛塾塾長も、「半分ずつ使やぁいい」とおっしゃられていますので、私はこの方法をお勧めします。半分ずつ使えば無駄もありませんし、使っていて「今日は大丈夫だけど次は持たないなぁ・・・」と感じたときに罪悪感無く半額で新品の道糸を使えます。この手法を使って、私は1巻きで釣行6~7回持たせています。ただし、私の場合、釣っている時間が平均3~4時間での回数です。丸一日12時間釣ったとすれば最低2回は切り落としますし、魚が沢山釣れれば切り落とす回数も増えますので、半巻きで丸1日分と考えればよいのではないでしょうか?
道糸をできるだけ安く、そしていい状態で使うために、ダイワ・シマノのスプールで150m巻きを半分ずつ使うことに適した下巻きの量を計算し、表にまとめました。道糸の下巻きでコスト半減はこちら。
PEの交換タイミングは、時間経過で強度的にダメになることはないので、ナイロンやフロロに比べてかなり長持ちすると思います。毎回ささくれ・ヨレなどをチェックして、気になる部分を切り捨てていき、その結果糸が足りなくなったら交換時期だと考えていいと思います。その分、リーダーはほぼ毎回交換なので、そちらにコストが割かれますね。
しかし、道糸は高価ですよ。エサの次にコストが掛かります。釣具屋に行ってこまめにセール品を探しておかないと通常の売値でばかり買っていられません。ハリスは半額セールとか多いですけどねぇ・・・